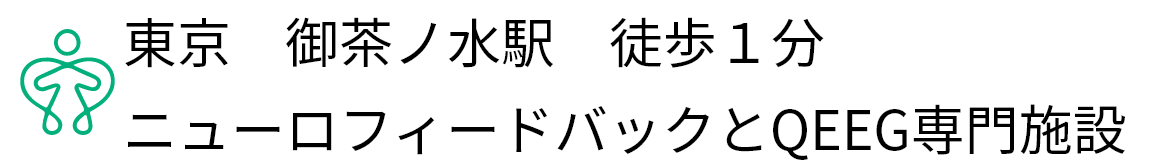うちの子、落ち着きがないのはなぜ?薬以外の方法で集中力を育むには

「椅子にじっと座っていられない」
「食事の時も、いつもソワソワ、体を動かしている」
「お友達との会話でも、お話が最後まで聞けないみたい…」
お子さんのそんな様子を見て、「私のしつけが足りないのかしら」「どうしてうちの子だけ…」と、ご自身を責めたり、一人で悩みを抱え込んだりしていませんか?
どうか、その手を止めて、少しだけこの記事を読んでみてください。
お子さんの落ち着きのなさは、決して「わがまま」や「しつけ」の問題ではありません。その背景には、お子さんならではの「特性」が隠れているのかもしれないのです。
この記事では、まずお子さんの落ち着きのなさが「なぜ」起こるのか、背景にある可能性を探ります。その上で、薬に頼らずに穏やかな集中力を「育む」ための具体的なアプローチを5つご紹介します。
原因がわかれば、対応策も見えてきます。
この記事が、お子さんへの理解を深め、明日からの関わり方を変えるきっかけになれば幸いです。
「落ち着きのなさ」の背景にあるかもしれない3つの可能性
落ち着きのなさの理由は一つではありません。お子さんの状態を正しく理解するために、まず「なぜ?」の部分を一緒に見ていきましょう。
感覚の特性(感覚処理の問題)
私たちは、触れる感覚、体の位置を感じる感覚、揺れや傾きを感じる感覚など、無意識のうちに様々な感覚情報を脳で処理しています。この感覚の感じ方には大きな個人差があります。
- 感覚を求めるタイプ(感覚が鈍い・低反応)
体をわざと揺らしたり、貧乏ゆすりをしたり、姿勢を崩したり…。これらの行動は、実は鈍感な感覚を補うために、無意識に自分の脳に刺激を入れ、目覚めさせようとしているのかもしれません。「ここに自分の体があるぞ!」と確認しているのです。 - 感覚に敏感なタイプ(感覚過敏)
一方で、服のタグがチクチクして耐えられない、周りの物音や話し声が全部耳に入ってきてしまうなど、普通は気にならない刺激を過剰に受け取ってしまう子もいます。その不快感から逃れるために、ソワソワと落ち着かなくなってしまうのです。
脳の発達段階によるもの
行動にブレーキをかけたり、注意をコントロールしたりする脳の「司令塔」とも言える部分(前頭前野)は、20代にかけて、ゆっくりと発達していきます。
つまり、特に小さなお子さんの場合、脳のブレーキ機能がまだ発達の途中であるのはごく自然なことです。
発達のスピードには個人差が大きいため、同年代の子と比べて少しブレーキが効きにくいのは、成長過程の一つの姿と捉えることができます。
発達特性によるもの(ADHDなど)
落ち着きのなさが、ADHD(注意欠如多動性障がい)をはじめとする発達特性に由来することもあります。
ADHDは決して病気や本人の努力不足ではありません。
たくさんの情報が入ってきたときに、どれに注意を向けて、どれを無視すればいいか、情報の交通整理をするのが少し苦手な状態です。
情報の交通整理が少し苦手な特性があることで、一つのことに集中し続けるのが難しくなったり、思いついたことをすぐ行動に移してしまったりするのです。
薬に頼らず「集中力」を育む5つのアプローチ
落ち着きのなさを無理に押さえつけても、うまくいきません。
お子さまの特性に合った方法で、穏やかな集中力を「育む」アプローチが必要です。
【感覚を満たすアプローチ】体を動かして脳を満足させる
特に、感覚を求めて体を動かしているタイプのお子さんには「ダメ!」と止めるのではなく、安全な形で体を動かしたい欲求を満たしてあげることが有効です。
脳が満足すれば、自然と落ち着きやすくなります。
- 勉強や宿題の前に:公園で思いっきり遊ぶ、トランポリンを10分跳ぶなど、体をしっかり動かす時間を作ってから勉強や宿題をする。
- 集中が必要な時に:時間を区切って、体を動かすようにする。
- 日常生活で:お手伝いとして少し重いもの(辞書や牛乳パックなど)を持ってもらう、休憩時間にぎゅっと抱きしめてあげる(圧覚刺激&愛着形成&承認欲求の充実)。
【環境を整えるアプローチ】脳の負担を減らす「足場」を作る
脳が情報処理に使うエネルギーを節約し、集中すべきことに力を注げるようにするには、環境をシンプルに整えてあげることが有効です。これを「足場作り(スカフォールディング)」と言います。
- 刺激を減らす:集中させたい時はテレビを消し、おもちゃが見えないように布をかけるなど、視覚・聴覚の刺激を減らす。
- 見通しを持たせる:「①宿題 → ②おやつ → ③ゲーム」のように、やるべきことを絵やカードで示し、先の見通しが立つようにする。
- 時間を区切る:キッチンタイマーを使い「タイマーが鳴るまでの15分だけ頑張ろう!」と短く区切ることで、集中へのハードルを下げる。
【体の中から整えるアプローチ】食事を見直す
脳の働きは、日々の食事と密接に関わっています。脳の働きを邪魔するものを減らし、必要な栄養を届ける視点で食事を見直してみましょう。
- アレルギー:すぐに反応が出るアレルギーや、気がつきにくい「遅延型フードアレルギー」が、気分のムラや集中力の低下の原因になっていることがあります。
気づかないうちに特定の食品が脳の炎症を引き起こしているかもしれません。特定の食品(例:乳製品、小麦グルテン、卵など)を食べた後に、様子(かゆくなっていないか、過度に興奮していないか、お通じ)に変化がないか、注意深く観察してみましょう。
また、一定期間、パンを食べないようにするなど、お子さんの様子に変化があるか見てみるのも一つの方法です。 - タンパク質不足:脳の神経伝達物質(やる気や落ち着きのもと)はタンパク質から作られます。肉、魚、卵、大豆製品が毎食しっかり摂れているか確認しましょう。
- ビタミン・ミネラル不足:鉄、亜鉛、マグネシウム、ビタミンB群の不足は鉄分や亜鉛、マグネシウム、ビタミンB群は、脳の働きをサポートする重要な栄養素です。
- 糖質の摂りすぎ:お菓子やジュース、白米などの摂りすぎによる血糖値の乱高下は、イライラや集中力低下に直結します。
【摂取に関する注意】オメガ3脂肪酸について
オメガ3脂肪酸(青魚の油など)は、症状が悪化するケースがあります。慎重に検討するようにしてください。また、オメガ3脂肪酸だけではなく、オメガ6系脂肪酸などの多価不飽和脂肪酸も、慎重に検討するようにしてください。
【専門的なトレーニング】ソーシャルスキルトレーニングと作業療法(OT)
専門機関で受けられるトレーニングも、お子さんの大きな助けになります。
- ソーシャルスキルトレーニング(SST):小集団の中で、イライラしたときの対処方法や、動きたくなったときの対処方法、お友達との関わり方や感情の伝え方など、社会的なスキルを具体的に学んでいきます。
- 作業療法(OT):作業療法士が、遊びを通して感覚統合を促したり、手先の不器用さを改善したりする専門的なリハビリテーションです。なお、症状によって適応外となるケースや作業療法をしなくても問題ないケースもあります。
【脳の状態からアプローチ】ニューロフィードバック
これまで紹介したアプローチに加えて、「どうして落ち着けないの?」という原因である脳機能そのものに直接働きかけ、脳が自ら落ち着き、集中する力を育むトレーニングがニューロフィードバックです。
ニューロフィードバックの具体的な流れ
- 【STEP1】QEEG検査で脳の状態を「見える化」する
最初にQEEG(定量的脳波検査)という検査で、脳の活動状態を客観的なデータとして測定します。QEEGにより、感覚の問題なのか、脳機能の特性なのか、落ち着きのなさの根本原因を探ることができます。 - 【STEP2】一人ひとりに合ったトレーニングプランを作成する
QEEGの結果に基づき、専門家がその子に本当に必要なオーダーメイドのトレーニングプランを作成します。「集中力を高める」「衝動性を抑える」など、目的に応じて脳の特定の場所をトレーニングします。 - 【STEP3】ゲーム感覚で楽しくニューロフィードバックトレーニング
ニューロフィードバックトレーニングは、頭に小さなセンサーをつけ、モニターを見るだけ。脳波が望ましい状態になると、モニターの映像が動いたり、音楽が鳴ったりします。お子さんは、まるでゲームをしているような感覚で、楽しみながら、無意識のうちに自分の脳を最適な状態にコントロールする方法を学んでいきます。
まとめ:本当の原因を知ることが、最適なサポートの第一歩
今回は、お子さんの落ち着きのなさの背景と、薬に頼らずに集中力を育む5つのアプローチをご紹介しました。
- 体を動かして感覚を満たす
- 環境を整えて脳の負担を減らす
- 食事を見直して体の中から整える
- 専門的なトレーニングでスキルを学ぶ
- ニューロフィードバックで脳機能そのものに働きかける
「いろいろな方法があるのは分かったけれど、うちの子の本当の原因はどれなんだろう?」
きっと、そう思われたことでしょう。
その答えを見つけるための最も確実な第一歩は、専門家と一緒に「お子さんの脳の状態を客観的に知る」ことです。
推測で様々な対策を繰り返すのではなく、QEEG検査で脳の状態を客観的なデータとして見ることで、お子さんへの理解が深まり、的確なサポートの道筋が見えてきます。
一人で悩まず、抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。専門家がお子さんの様子を丁寧にお伺いし、その子に合った最適なサポートプランを一緒に考えていきます。
初回面談のご予約はこちら